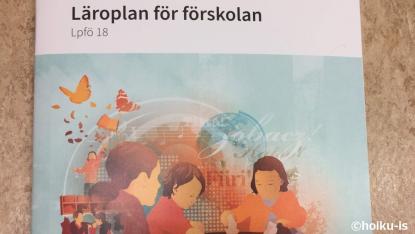>>連載一覧はこちら
「スウェーデンのナショナルカリキュラム」の続き
前回のおさらいです。 スウェーデンも日本も幼児期の教育を人生の土台作りと位置づけて、この時期の子どもの発達に合わせた活動を行うことが「ナショナルカリキュラム(以下カリキュラム)」で定められています。特に、この時期の子どもは発達に個人差があるので、スウェーデンの場合は「全ての子どものニーズに合わせて」活動するということが強調されています。実際にどう使われているのか?
今回は、カリキュラムがどんな風に現場で使われているのか、私の職場の例を紹介します。
- 社会と関わる力
- 言葉とコミュニケーション
- 文化と表現
- 持続可能な社会の実現
- デジタルスキル
- 数学
- 自然科学
- 技術
- 外活動
- 遊び
年度初めの会議で活動の展開を計画

私は1〜3歳児クラスで働いているので、「数学」の領域では、階段を登る時など日々の生活の中で自然に数をかぞえることをする、大きさの比較を示してみせる、という行動指針と具体的な活動の方向性をこの場で決めました。
日々の活動は、3人チームで働く同僚と週に1回1時間程度のミーティングで週間計画を立てます。保育計画のように詳しく決めることはなく、その日にどこに行くのかを決める程度です。ねらいを立てて活動するというよりは、その日の活動の中でのできごとを振り返って、どういう経験をしたのかを拾って記録するというやり方になります。この記録は、毎日保護者との連絡用アプリに投稿したり、正式な活動記録文書として残しています。
次回は今年の7月に改訂になったカリキュラムの中のホットな話題をお伝えします。
▼その他のスウェーデンの幼児教育コラム