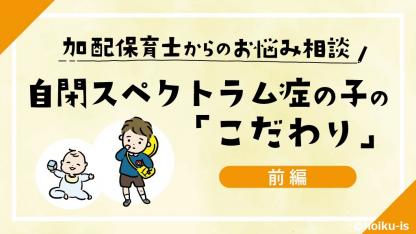>>連載の記事一覧はこちら
発達障害のある子と「ルールがある遊び」の対応方法
前回は「発達障害のある子のルールがある『遊び』への参加についての考え方」として、まず、「安心できるようにする」というお話をしました。 今月は、「「遊び」の指向性」と「対人指向性」の軸で「遊び」を考える」ということをお話しします。子どもに、
1、自分から
2、満足するところまで
3、楽しむことができる
という3つの要素を充たす「遊び」を補償するにあたって、保育士が子どもに「遊び」を提案したり、集団遊びに誘ったりすることがあります。
適切に働きかけるには、どんな「遊び」がその子にとって3つの要素を満たす「遊び」なのかについて、ある程度見当をつけておく必要があります。
ここで有効なのが、「『遊び』の指向性」と「対人指向性」の軸で「遊び」を考える方法です。

「遊び」の指向性=どういう「遊び」を好むか
定型発達の子は、想像力を働かせる遊び、さらに「遊び」を変化させることを楽しむことが多いです。おままごとなどがその例です。それに対して発達障害のある子の中には、想像力を働かせて遊ぶことや変化を好まず、例えば、ミニカーを前後に動かしたり、並べたりするなど、一定のパターンを繰り返し楽しむことが好きな子どもがいます。
一定のパターンを繰り返すことが楽しいのです。心地よいのです。そのような子どもには、「変化」は楽しいことではないのです。
「同じことを繰り返すことが楽しい」という「『遊び』の指向性」は私たちには理解しにくいかもしれません。
しかし、子どもの「遊び」を補償する、すなわちその子が3つの要素を充たす「遊び」ができるよう支援する、には「同じことを繰り返すことが楽しい」という「『遊び』の指向性」があることは覚えておきたいことです。

「対人指向性」=仲間との「遊び」を好むか、ひとりで遊ぶのを好むか
仲間関係を好み、安定した人間関係を作っている子どもにとって、集団での「遊び」は「楽しみ」であり、「満足」するものです。ですから、仲間で遊ぶことを好みます。しかし発達障害のある子、特に自閉症スペクトラム障害の子どもの場合は、安定した仲間関係がなかなか作れず関係が流動的で、時には仲間との関係が緊張やストレスを感じるものであることがあります。
そのような子どもにとっては、集団での「遊び」は「楽しくない」、ひとりで遊ぶのが「好き」で「満足」です。だから仲間で遊ぶよりひとりで遊ぶことを好みます。
「遊びの指向性」と「対人指向性」から「遊び」を提案し、子どもを支援する
続きは、ほいくisメンバー/園会員限定です。
無料メンバー登録でご覧いただけます。