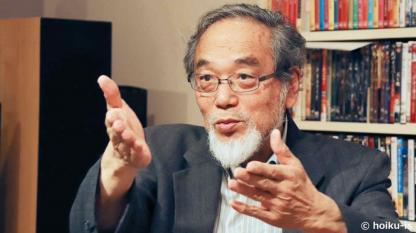無形文化遺産になった和食

中田さんは、「和食の離乳食」を中心に講座開講やレシピ本出版をされていますよね。和食の良さは何ですか?
実は、2013年(平成25年)に和食がユネスコ無形文化遺産になったのはご存知ですか? 素晴らしいことですよね。ではなぜ文化遺産になったのか。その理由は、「和食が絶滅の危機にあるから」なんです。
私が園で子どもの連絡帳を見ていても、和食メニューを提供する家庭は少ないですね。なので、ぜひ園で提供する離乳食で子どもたちに和食を伝えていってほしいという想いも持っています。
どこかホッとする味の和食を、ぜひ味わってほしいですね。園で提供する離乳食のレシピで、おすすめのものはありますか?
ぜひ旬の食材を使ってほしいと思います。例えば今は夏なので(取材は8月初旬)、冬瓜を使った煮物がおすすめです。鶏のささ身やひき肉など、タンパク質たっぷりのものと合わせて作る煮物はおいしいですよ。冬瓜は、もしかすると大人でもあまり口にしたことがないかもしれません…
そうですよね(笑)。“家庭であまり食べないもの”を、園で経験させてあげるのがいいかなと思います。その他にも、最近はお魚料理や果物も取り入れている家庭が少ないようです。これらも旬で出てくるものなので、ぜひ取り入れてみてください。一番「おいしい」と感じる五感は…
 (写真:離乳食インストラクター 中田馨さん)
(写真:離乳食インストラクター 中田馨さん)園で離乳食に関わる大人には、保育士以外にも栄養士や調理師がいますね。作るときの注意点はありますか?
まずは、子どもに合わせた大きさ・柔らかさ・なめらかさであることです。味付けもとても重要ですね。よく保護者から「子どもが離乳食を食べない」と相談を受けて、「子どもがケチャップ好きだから使ってみてください」とアドバイスをする先生もいたりするのですが、味を濃くして食べさせるというのは避けてください。濃すぎず、素材の味を感じられるようにしてみましょう。
下処理もしっかり行ってくださいね。少し面倒かもしれませんが、豆類は薄皮を取り除く、きゅうりやなすの皮を剥く、ひき肉は湯通しして油を取り除くなどです。これは、子どもが飲み込みやすくすることはもちろん、消化を助けてくれることにもなります。
実際に作るのは調理スタッフですが、出来上がったものを保育士が目で見て確認することも大切ですね。
保育士さんは、調理スタッフさんと想いを合致させておくことが重要だと思います。よくあることで、調理スタッフさんは手づかみ食べをしてほしかったメニューだったのですが、保育士さんがスプーンで与えてしまった…とか。お互いに想いがあるはずなので、意思疎通しておくと離乳食もスムーズに進みますよ。子どもたちの様子を一番よく分かっているのは保育士さん。「これはよく食べた」「これは少し早かったかも」など、その子に合わせた離乳食の状態を伝えてほしいです。

園の規模が大きかったり忙しいときには、離乳食を与えることが作業になりがちだと思います。そのような中では大変かもしれませんが、子どもたちが「食事が楽しいな」と思えるように出来るだけ保育士さんも楽しく食事を提供してみてください。
保育士が感じる“離乳食の悩み”

遊び食べは必要
遊び食べに関する悩みは多いと思います。「遊び食べで給食が進まない…」どうすれば良いでしょうか。
子どもにとっては、それが楽しくて仕方がない時期なんですよね。それは食に興味を持っている証拠でもあるので、ある程度自由に遊ばせてあげることも必要ではないかと思います。ただこれが、「遊びに変わったな」と思ったら食事を撤収する。“食への興味”と“遊び”を見極めます。この時期は、“全部食べさせなきゃいけない”という考えは一旦頭の隅に追いやりましょう。確かに食べることは大切ですが、口に入らなかったら仕方ない(笑)。それを30分、40分とかけて食べさせようとしては、保育士も子どももストレスになってしまいます。ある程度の時間を決めて、切り上げる潔さも必要です。
好き嫌いは、成長の証
好き嫌いが多い子どもに対しては、どうすれば良いですか?
私は、子どもが「これは好き」「これは嫌い」って認識していることがすごいと感じています。好き嫌いも脳の発達の証で、喜ばしいことですよね。だからといって嫌いなものをすべて除去すれば良いわけではなく、やはり経験してほしい。そこで、なぜ苦手なのかを観察してみましょう。
もしかすると離乳食の段階があがって、大きさが変わって食べづらいのかもしれませんし、食感が苦手なのかもしれません。私が園でよく言っているのが、離乳食完了期の子どもでも「食べなかったら、一度初期や中期に戻してごらん」と。そうすると食べられる子は結構多いんですよ。
味ではなく、食べづらさの問題ということもあるのですね。大人と同じで食わず嫌いの子も中にはいますが、そのときはどうしますか?
保育士さんが一緒のものをその場で食べてみることも効果的です。子どもを意識せず、自然に「おいしい」と食べていると、興味を持って口に入れてくれることもありますよ。また、よく食べるお友だちの隣だとつられて食べたりする子も多いです。
丸呑みするときは、アプローチを再確認

保育士さんには、「子どもが食事を丸呑みする」という悩みも多いようですね。
そのときは、スプーンに盛る量を減らしてみると良いかもしれません。てんこ盛りになっていると噛めずに飲み込んでしまうことがあります。
また離乳食の時期ごとの進め方の中でお話ししましたが、保育士さんのスプーンの使い方を確認してみてください。食材は唇で取り込むように与え、スプーンは水平に引く。噛みやすいようにアプローチしましょう。
その他にも、子どもが噛んでいる最中に口の前に食材を持っていくと、急いで食べる癖がついてしまい噛まないようになることもあります。食事は口の中からなくなってから与えるようにしましょう。
保育士さんが一緒に「もぐもぐ」という動きをして見せるのも効果的ですよ。
「もぐもぐ」を見せるということで言うと、現在は新型コロナウイルスの影響で保育士さんがマスクをしていて、噛んでいる様子が見せられず丸呑みするようになった…ということがあるそうです。
私の知人の保育士は、食事のときだけフェイスシールドに変えていると言っていました。そういう工夫も、今の状況では必要かもしれませんね。いろいろと対策が必要な時期ですが、出来ることをやってみてほしいと思います。「完食させる」と思わない
他にも現場でよく挙がる悩みはありますか?
おかずばっかり、お米ばっかり、という「ばっかり食べ」ですね。汁ものをすぐ混ぜちゃうとか(笑)。無理して食べさせるのではなく、「一口だけでも他のものを食べて経験しておこう」くらいの気持ちでいましょう。それ以外では、食事中の立ち歩きについて悩んでいる先生も多いですね。立ち歩いてしまう場合は、追いかけてその場で食べさせることは窒息の危険性にも繋がるので避けてください。
「座りなさい!」と叱ったり、声をかけすぎると子どもは逆に楽しくなってしまうので、あまり反応しすぎないでおくと良いですよ。ただし、口の中にものが入ったまま立ち歩くのは危険なので気を付けてくださいね。
給食の完食については、先生ごとで考え方の違いもあり苦労することが多いように感じます。
そうですね。しかし、先ほどもお話ししたように離乳食や幼児食には完食を求めないでおきましょう。この頃は出された食事が適量かどうかは自分では分かりません。自分が食べられる適量が分かり、完食できるようになるのは小学生になってからと考えておいてください。大人も同じで、人によって適量は違いますよね。だから「無理に完食しなくても良いんだ」という認識を先生たちの中でも持っておくと、完食させなくちゃいけないというストレスがなくなるのではないでしょうか。
食事で人生を豊かに
最後に、子どもの食に関わる保育士の皆さんに伝えたいことはありますか?
保育士さんが楽しく食事を提供することで、子どもも楽しいと感じるようになり、苦手なものもチャレンジしてみようかという気持ちになってくるはずです。食事が楽しいことで人生はより豊かになります。そのお手伝いを、保育士さんたちにぜひしていただきたいと思っています!
食は幸せにつながる大きなポイントですね。ありがとうございました!
【関連記事】
1978年生まれ。中田家庭保育所施設長、一般社団法人 離乳食インストラクター協会代表理事。保育士、離乳食インストラクターとして企業の育児コラム執筆。関東・関西を中心に食育の講演会などを行う。二児の母。
<著書>
『いっぺんに作る あかちゃんと大人のごはん』
<コラム連載>
『AERA dot.』『AERA with baby』『小学館 Hagukum』『ベビーカレンダー』など
<離乳食講座>
離乳食インストラクター協会2級講座
<協会HP>
https://babyfood-instructor.com/