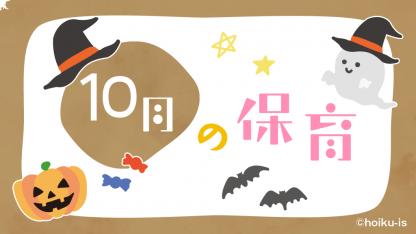ひな祭りの由来と伝え方・ねらい
ひな祭りは、“桃の節句”とも言われ「女の子のお祝い」というイメージがありますよね。その由来はどのようなものなのでしょうか。まずは保育者の方で由来や風習についてしっかりと理解してから、子どもたちに伝えていきましょう。また活動にあたっては、ねらいを持って計画を立てて進めましょう。ひな祭りの由来

その後、もともと貴族の女の子たちの間で行われていたままごとのような「ひいな遊び」と次第に合わさるようになり、ひな祭りになったと考えられています。
現在のひな祭りは、雛人形を飾ることで女の子の健やかな成長を祈る行事となっています。
また「節句」は季節の節目となる日のことですが、もともとは中国から伝わったもの。古くから、厄払いや無病息災の祈願、健康や不老長寿の祈願などの行事を行う日として、今日まで伝えられてきています。代表的なものとしては、1月7日の「人日(じんじつ)の節句(七草の節句)、5月5日の「端午の節句(菖蒲の節句)」、7月7日の「七夕の節句(笹の節句)」などがあります。どれもお馴染みのものですよね。
ひな祭りの風習の意味

【流し雛/ながしびな】
古くからある、人の形(形代=かたしろ)に見立てた木の葉に邪気を移して川に流す風習で、ひな祭りの元になったと言われています。現代でも各地で行われており、下鴨神社(京都)の流し雛などが有名です。
【雛飾り/ひなかざり】
現代のひな祭りでは、女の子の健康と幸せへの願いを込めて、ひな人形を飾るのが風習となっています。もともとあった流し雛の風習が、次第に女の子の健やかな成長を願うためにひな人形を飾るという形に変化し、江戸時代頃に定着したと言われています。
【桃の花】
ひな祭りは別名「桃の節句」とも言われ、ひな飾りにも桃の花は欠かせません。桃はもともと中国から伝わった植物で、古来中国では邪気を祓う力があるとされてきました。日本でも長寿を象徴する縁起の良い花になっていることと、ひな祭りの時期にちょうど花が見ごろを迎えることもあり、桃の花が飾られるようになったと言われています。
ひな祭りの食べ物の意味

【ちらし寿司】
長生きを意味するエビ、穴が開いていて見通しが立つことを示すレンコン、「まめに働く」という意味の豆など、中に入っている具材に意味があります。また、たくさんの具材が入ることから、「食べ物に困りませんように」という意味が込められているとも言われています。
【菱餅】
3色の菱餅には、一色ずつ意味があります。
- 赤色(桃色):魔除け/桃の花
- 白色:清浄/雪
- 緑色:健康/草の芽、大地
【はまぐりのお吸い物】
はまぐりは、対になっている貝殻同士でないとぴったり組み合わないと言われています。決して他の貝と合うことがないことから、「相性の良い相手と幸せな人生を送ることができる」という意味が込められています。
また、平安時代に始まった遊戯「貝合わせ」に使われていたことが、ひな祭りの祝い膳としてはまぐりのお吸い物が食べられるようになった由来とも言われています。
【ひなあられ】
菱餅と同じくカラフルで華やかな「ひなあられ」。3色のものは菱餅と同じ色と由来です。また、赤(桃)・白・緑に黄色を足した4色のものもあり、この場合は四季を意味していると言われています。
子どもたちへの伝え方

【伝え方の一例】
- ひな祭りは、女の子が元気に大きくなれるように願う日
- 季節が変わるときにはお祝いをする
- お人形や桃の花は、悪いものを取ってくれる
- 元気に過ごせるように、お祝いの食べ物を食べる
 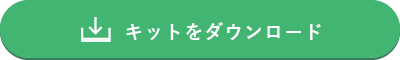 |
ひな祭り活動のねらい
ひな祭りは、子どもたちも楽しみにしている行事です。しかし、保育園や幼稚園、認定こども園の活動として取り入れるときはきちんと計画を立てて、ねらいを持って行わなければいけません。ねらいの例を挙げてみました。<ねらいの例>
- ひな祭りの由来を知り、日本の伝統的な文化に触れて親しむ。
- 貝合わせ遊びや行事食、歌で古くからある風習に親しみ、お友だちや保育者との交流を深める。
- 暦の区切りに行う行事ということを伝え、季節の移り変わりについて関心を持つ。
ひな祭りの遊び
ここからは、ひな祭り行事におすすめの活動をご紹介していきます。まずは遊びから。貝合わせゲーム
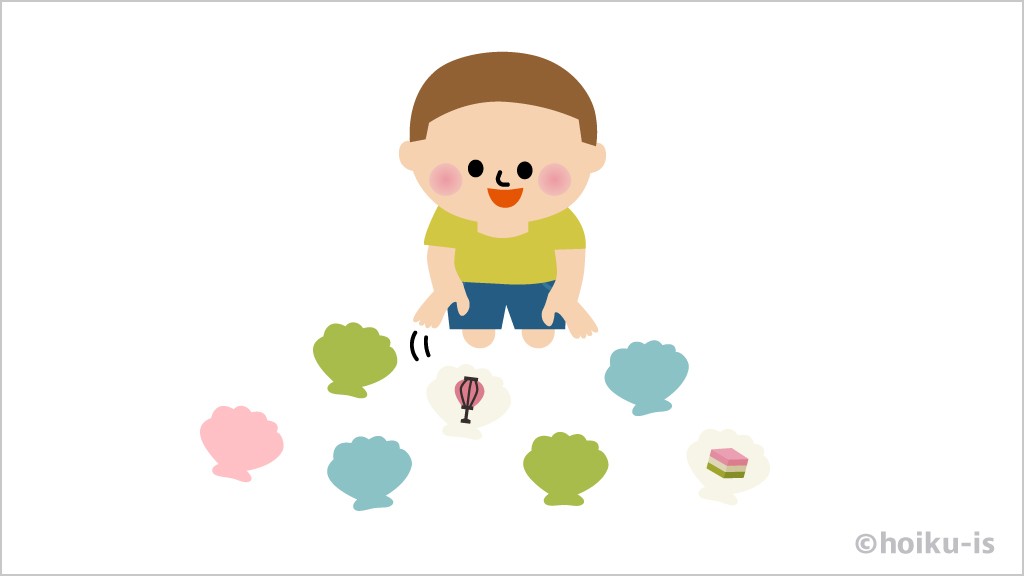
【用意する物・道具】
- 画用紙
- カラーペン
- ハサミ
- 画用紙に貝の形をたくさん描きます。その貝の形の中に、2枚1組になるように絵を描いておきます。
- 貝の形をハサミで切り抜きます。
- 切り取った貝を裏返して、バラバラに置きます。
- 神経衰弱のように、順番に貝をひっくり返して、同じ柄が2枚揃ったらその2枚をもらいます。
- 最終的に、一番枚数を多く持っていた子の勝ちです!
 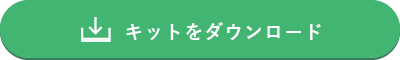 |
ひな祭りの歌
続いて、ひな祭りの活動の導入に使える歌をご紹介しましょう。うれしいひなまつり


作詞:サトウハチロー(別名:山野三郎)
作曲:河村光陽
>>歌詞はこちら
ひなまつりプリンセス
キッズソングでお馴染みの新沢としひこさん作詞・作曲のひなまつりソング。「もものおひめさま~」「ピンクのリボンをつけておいわいしたの~」などのフレーズが可愛いですよね。作詞・作曲:新沢としひこ
>>歌詞はこちら
ゆめみるおひなさま
こちらは人気音楽ユニット・ケロポンズさんによるひなまつりソングです。「おんなのこのゆめ」として、可愛らしい願いが歌われています。作詞・作曲:増田裕子
>>歌詞はこちら
ひな祭りを楽しむ製作・壁面アイデア5選
続いては、子どもたちと楽しめるひな祭りの製作アイデアをご紹介します。①きせかえおひなさま【手作りおもちゃ】
くるくると回りながら、着物の柄が変わるひな人形の製作アイデアです。今回はひな祭りらしく、マスキングテープで華やかに模様付けしてみました♪ シールを貼ったり、絵の具で色付けしたりと、自由にアレンジを楽しんでみてください。
②ひな人形の吊るし飾り【部屋飾り】
ひな祭りの飾りにおすすめ! 吊るし雛の製作アイデアです。吊るし雛は、庶民にも身近なひな飾りとして長く親しまれています。ちりめん柄の折り紙で作った雛人形(ひな人形)と、花をイメージした飾りをつなげています。顔の部分は、子どもたちで自由に描いてみるのも一人ひとり違った作品に仕上がるのでおすすめです。③ふわふわ!壁掛けおひなさま【部屋飾り】
コロンとした形がかわいい、ひな人形の吊るし飾りです。子どもたちの成長を願うひな祭りの壁面製作にぴったり。紙皿にたっぷりの綿を敷くことで、もこもことしたボリューム感のある作品に仕上がります。④足形お雛様【乳児向け製作アイデア】

【対象年齢】0歳/1歳/2歳
【材料】
- 絵の具
- 画用紙
- 子どもの顔写真(イラスト)
- 画用紙に、絵の具で子どもの足形をとる
- お雛様、お内裏様の顔を作り、足形を服に見立てて画用紙に貼り付ける
- 衣装や頭の飾り、周りの装飾をすれば完成
⑤十五人飾りのおひなさま【壁面】

イラストを描いてくれたのは、保育・幼児教育分野で活躍する人気イラストレーター・クリエイターの星野はるかさん。ほいくisでは、Webセミナーでもお馴染みですね。
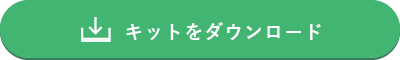
ひな祭りを楽しむ絵本
ひな祭りをもっと楽しむために、絵本の読み聞かせを行ってみるのもいいですね。みんなでおひなさま!

作:きむら ゆういち
絵:ふゆの いちこ
出版社:教育画劇
くまの「くー」と「まー」がお雛様を作ります。そのために使ったのは…? 低年齢児から楽しめるしかけ絵本になっています。
まずはひな祭りを楽しむところから、というときにぴったりです。かわいくはっきりとしたイラストや、生き物が登場する内容に子どもたちもワクワクすること間違いなしです。
おひなさまのいえ

作:ねぎし れいこ
絵:吉田 朋子
出版社:世界文化社
雛人形のお店から、「自分たちの家を探しに行こう!」と雛人形たちが飛び出します。なかなか家が決まらない中、やっと見つけたのはボロボロの家で…。
フェルト、ちりめんなどを使用して描かれたイラストがとてもかわいく魅力的。「流し雛」のお話しが入りつつ、ユニークなストーリーに子どもだけでなく大人も見入ってしまいそうな一冊です。
おいしいおひなさま

文:すとう あさえ
絵:小林 ゆき子
出版社:ほるぷ出版
ねずみちゃんと、りすちゃんと、うさぎちゃんと、たぬきちゃんは、おひなさまが欲しくてたまりません。そこで、自分だけのおひなさまを作ることにしました。
それぞれが作る「おいしそうなおひなさま」は、どれもとってもユニークで可愛い! 思わず欲しくなってしまいます。保育園や幼稚園でおひなさまを手作りするときのヒントにもなりそうです。
ひなまつりのちらしずし

作:宮野 聡子
出版社:講談社
ひなまつりパーティーの日、きみちゃんはお母さんと一緒に「ちらしずし」を作ります。ちらしずしの材料一つひとつに、いろいろな意味が込められていると知ってきみちゃんは驚きます。
ちらしずしの材料に込められた意味を、絵本を通して学ぶことができます。イラストが分かりやすく、行事絵本としておすすめしたい1冊です。
ワクワクするひな祭りを
行事を通して日本の伝統を知ることも良いですが、楽しむことも忘れずに。子どもたちとワクワクするようなひな祭りを過ごしてくださいね。【関連記事】