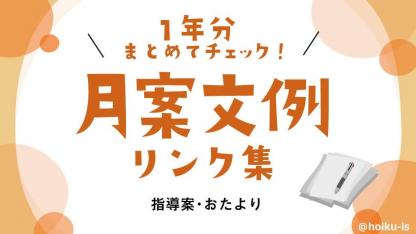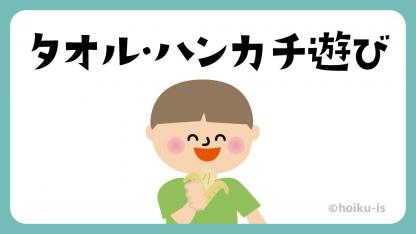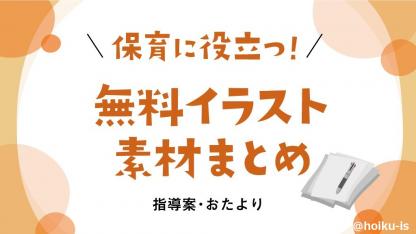保育のポイント【1歳児・11月】
11月になると寒い日が増え、葉が本格的に紅葉して秋らしい自然を楽しめます。戸外活動では実際に自然に触れたり色を楽しんだりしながら、今の季節だけの楽しみを味わってくださいね。また11月頃に生活発表会を開催する園では、ねらいをしっかりと立てて子どもたちの成長を感じられる機会になると良いですね。

ねらい【1歳児・11月】
- 戸外で身体を動かし、元気に遊ぶ。
- 身の回りのことを自分の力でやろうとする。
- 他児の気持ちを感じ取り、関わろうとする。
- 他者との関わりや言葉のやり取りの楽しさを感じる。
- 秋の自然に興味を持つ。
- 生活発表会でリズム遊びを楽しんで披露する。
- 絵本の言葉を繰り返し、物語に親しむ。
- 指先を使った製作や遊びを楽しむ。
内容/五領域対応【1歳児・11月】
- 公園に行き、走ったりボールを投げたり坂道を登ったりしながら、全身を使ってのびのびと遊ぶ。(健康)
- 靴を自分の靴箱に入れたり、脱いだ服をロッカーに片づけたりして、保育者の真似をして身の回りことを行う。(健康)
- 他児が欲しがっている玩具を「どうぞ」と持ってきて手渡したり、泣いているところに行って頭を撫でたりする。(人間関係)
- ままごとをする中で、「どうぞ」「めしあがれ」など言葉をかけてやり取りを楽しむ。(人間関係・言葉)
- 木の実や落ち葉を拾って手作りバッグに集めたり、葉っぱのうえで寝転がったりして自然を楽しむ。(環境)
- 生活発表会では「サンサン体操」の曲で音に合わせて身体を動かし大きく動く。(環境・表現)
- 繰り返しの言葉が出てくるお話を好み、保育者の真似をしたり、絵を指さして言葉を発したりしながら絵本を楽しむ。(言葉)
- 丸い枠の中にシールを貼ったり、粘土で「おだんご」「おにぎり」など自分で考えたものを作ったりして、指先を使う遊びに集中する。(表現)
| ※「内容」については、例文の最後に保育所保育指針にある五領域のどれに対応しているか表示をしています。 ・健康(心身の健康に関する領域) ・人間関係(人とのかかわりに関する領域) ・環境(身近な環境とのかかわりに関する領域) ・言葉(言葉の獲得に関する領域) ・表現(感性と表現に関する領域) |
内容/養護【1歳児・11月】
- 着替えの中で難しいところだけ手伝い、その他は最後までやりたい気持ちを受け止めながら見守る。
- のびのびとやりたいことを表現できるよう、安心できる環境を整える。
- 排泄前の不快感を保育者に伝えてくる際は、トイレでの排泄を促し、必要に応じてサポートをする。
- 上着を着ようとするなど戸外活動の準備を自分でするようになったら、声掛けをして習慣付けを促す。
環境構成・保育者の配慮【1歳児・11月】
- 安全な環境の中で好きなように動けるよう、子どもの足で歩きやすい道が多い公園を選んで散歩に行く。遊び始める前には安全チェックを行う。
- 子どもの目の前で片付けをしたり、子どもと一緒にロッカーまで荷物を持って行ったりして、保育者がお手本になる。
- どのようなときにどう接するのか子どもが自然にイメージできるように、保育者は子どもの気持ちを代弁しながら関わる。
- 子どもが言葉のやり取りの楽しさを感じられるよう、保育者は積極的に感情を表現する言葉を発する。
- どんぐりや葉っぱを集められるように牛乳パックで作った手作りのバッグを持って散歩へ行く。
- 子どもがのびのびとリズム遊びできるように、普段の遊びの中で好きな動きを取り入れて振りをつける。
- 分かりやすい言葉が繰り返されていて、子どもの身近なものが題材になっている絵本を用意する。
- 塗り絵コーナーに新しくシール貼りを取り入れる。粘土は遊びが広がるようにゼリーカップやカラー粘土も準備する。
予測される子どもの姿【1歳児・11月】
- 坂道やでこぼこ道なども上手に歩けるようになり、子どもにも自信がついていろいろな場所へ行こうとする。
- 最初は自分でやりたがらなかった子も、保育者の様子を見ているうちに真似して一緒にやるようになる。
- 普段保育者が子どもにしている接し方を真似して「痛かったね」「大丈夫?」などと声をかけながら他児に関わろうとする。
- 保育者の言葉を聞いて嬉しそうにしたり、満足気な表情を見せたり、相手の言葉の意味をしっかりと理解するようになる。
- 自分のバッグいっぱいにドングリを集めながら、集中して遊ぶ。
- 馴染みのある曲でのびのびと自由に身体を動かす姿が見られる。
- 絵本「だるまさんシリーズ」を気に入り、読んでいるうちに内容を覚えて真似するようになる。
- シール貼りをする中で、線に沿ってきれいに貼る子もいれば、大胆にはみ出して貼っていく子もいて、個性が現れる。
前月の子どもの姿【1歳児・11月】
- 食事前の準備や片付け、おもちゃの整理などを積極的に行い、身の回りのことを自分で行うようになってきた。できないことがあっても諦めずに挑戦する姿も増えた。
- 指先が器用になり、ちぎり絵製作を楽しんでいたので、今月も引き続き指先を使う遊びを行う。
家庭や地域との連携【1歳児・11月】
- 冬が近づき、インフルエンザの流行も心配されるため、家庭での対策はもちろん園の対策にも引き続き協力してもらうよう求める。
- 子どもが「自分でやりたい」時期なので、保護者にも見守ってもらえるように園での様子や関わりを共有する。
健康や安全【1歳児・11月】
- 歩く範囲が広がり転倒なども見られるため、園外活動では石やたばこの吸い殻、ガラス片などが周囲にないか確認してから遊び始める。
- 子どもが多い公園に行くことは避け、園の周辺を散歩する、人が少ない時間に行くなど工夫して遊ぶ。
食育【1歳児・11月】
- 安心して食事ができるように、保育者は目を見て声をかけながら食事介助をしていく。
- さまざまな食材や食感に挑戦できるように、調理スタッフと連携していく。
今月の行事【1歳児・11月】
- 身体測定
- 避難訓練
- 生活発表会
- お誕生日会
今月の遊び【1歳児・11月】
いろいろな身体の使い方を覚え、身体を動かすことが楽しい時期になってきます。思いっきり発散できるよう、広々した場所での触れ合い遊びや運動遊びがオススメです。- タオル・ハンカチ遊び
- こんなことできるかな?
- フラフープあそび(けんけんぱ・ジャンプ)
- 風船タッチ
- サーキット遊び
今月の歌・手遊び歌・体操【1歳児・11月】
11月の歌
- げんこつ山のたぬきさん
- ぞうさん
- おなかのへるうた
- かみなりどんがやってきた
11月の手遊び歌
- ずっとあいこ
- コンコンきつね
- にくまんあんまん
- 3びきのこぶた
11月の体操
- フルフルフルーツ
- とんがりたいそう
- いんぐりもんぐり
- アキレスケンタウルス体操
今月のおすすめ絵本【1歳児・11月】
- あきぞらさんぽ
- どんぐりとんぽろりん
- えんやらりんご
自己評価【1歳児・11月】
10月は少しずつ気温が下がり始め、過ごしやすくなっていきましたね。外遊びや自然遊びを通して、季節の移り変わりを感じるような活動ができていたか振り返ってみましょう。今年度も後半に入ったので、生活習慣や身の回りのことなど、自分でできることも増えてきたのではないでしょうか? 「自分でできる」という自信が成長に繋がっていくので、進級や進学に向けて少しずつできることを増やしていくような声かけもできていると良いですね。
2023年度版フォーマットのダウンロード【1歳児・11月】
ほいくisメンバー登録(無料)をすると、Excel形式で“そのまま使える”月案/週案フォーマット(月週案)を無料でダウンロードすることができます。また、文例だけプリントして使いたい方のためにPDF版もご用意しました。ぜひご利用ください。
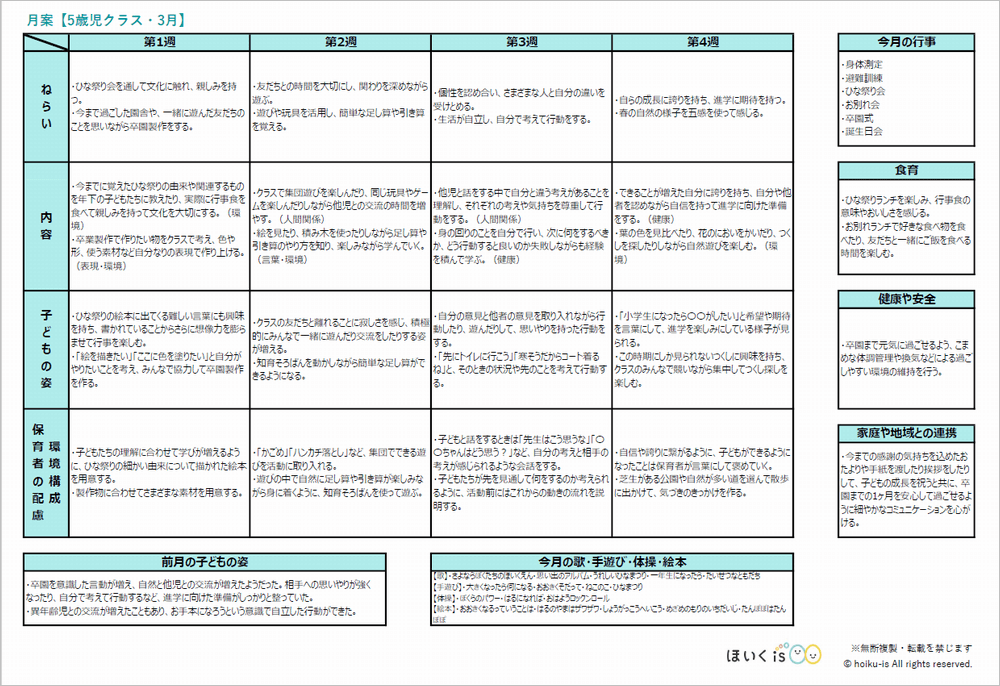
PDF版の月案文例【1歳児・11月】

自分の言葉で作る意識を
参考文例をお届けしましたが、あくまで指導計画は自分の言葉で作ることが大切です。一つひとつの事例を参考にしながら、少しずつ自分の考えを入れていくよう工夫しましょう。【関連記事】
>>指導案・おたより一覧