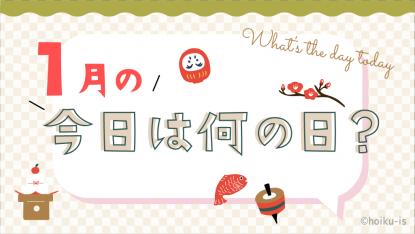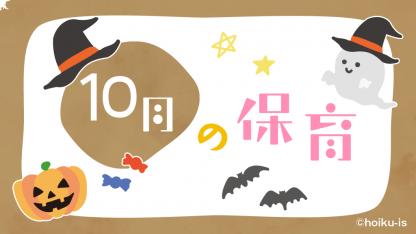節分の由来と伝え方・ねらい
昔からある伝統行事である節分は、ひな祭りやこどもの日、七夕などと並んで園でもさまざまな取り組みが行われる行事です。まずは保育者の方で由来や風習についてしっかりと理解してから子どもたちに伝えていきましょう。また活動にあたっては、ねらいを持って計画を立てて進めましょう。節分の由来

旧暦では春を1年の始まりとして考えていたため、4つの節分の中でも立春の前日はとても重要な日でした。そのため、次第に節分が2月3日頃(年により日付は変わる)だけを指すようになったと言われています。
立春は、中国古来の暦「二十四節気(にじゅうしせっき)」の1番目にあたり、春の気配が立ち始める日とされています。現代の日本では、太陽の地球に対する角度を国立天文台が観測して日にちを決めているため、年によって日付は変わります。そのため、「立春の前日」である節分の日付も年によって変わります。2024年(令和6年)以降の節分の日程は以下の通り。
- 2024年(令和6年)→2月3日(土)
- 2025年(令和7年)→2月2日(日)
- 2026年(令和8年)→2月3日(火)
- 2027年(令和9年)→2月3日(水)
節分の風習~豆まき・柊鰯・恵方巻の意味

【豆まき】
古代中国で邪気祓いのために行われていた、桃の木で作った弓矢を射る「追儺(ついな)」という行事が日本に伝わり、豆まきとなったそうです。豆を使用する理由として、鬼の「魔目(まめ)」にめがけて豆を投げると「魔滅(まめ)」になるからだと言われています。「鬼は外」「福は内」の掛け声に合わせて、園でも豆まきを楽しんでみてください。
【柊鰯/ひいらぎいわし】

【恵方巻/えほうまき】
節分ランチとして給食に提供されることもある恵方巻。その年の福の神様がいると言われる方角(恵方)を向いて、太巻きを切らずにそのまま食べることで、無病息災などを願います。もともとは関西地方の風習で、全国的に知られるようになったのはごく最近のため、知らなかったという方も多いかもしれませんね。
食べるときは「無言で願い事を思い浮かべながら」と言われていて、実践している方も多いのではないでしょうか。園で子どもたちと行うときは、サイズや太さなどに注意して楽しんでみてくださいね。2024年(令和6年)の方角は、東北東のやや東です。
子どもたちへの伝え方

【伝え方の一例】
- 節分は春が来る前の大切な日
- 季節が変わるときには悪い鬼がやってくる
- その鬼を退治するために豆をまく
- 鬼は、煙のにおいや尖ったものが嫌い(だから柊鰯というものを飾る)
- 恵方巻を食べるときは、元気に過ごせるようにお願いをしながら食べる
節分の活動のねらい
節分は、子どもたちも楽しみにしている行事です。しかし、保育園や幼稚園、認定こども園の活動として取り入れるときはきちんと計画を立てて、ねらいを持って行わなければいけません。ねらいの例を挙げてみました。<ねらいの例>
- 節分の由来を知り、日本の伝統的な文化に触れて親しむ。
- 豆まき行事で古くからある風習に親しみ、お友だちや保育者との交流を深める。
- 暦の上で春に変わる区切りに行う行事ということを伝え、季節の移り変わりについて関心を持つ。
園で豆まきをするときの注意点

豆を食べない
昔から「歳の数だけ豆を食べる」と言われていますが、園の活動では子どもたちが豆を食べるようなことは避けましょう。固い豆は子どもの力ではかみ砕けずに、そのまま気管に入って窒息してしまう危険があります。消費者庁では、「5歳以下の子どもには豆類を食べさせないように」という呼びかけも行っています。豆まきをした後は、たとえ小袋であっても片付けをするなど、しっかりと管理をしながら行いましょう。
参考:Vol.580 硬い豆やナッツ類は5歳以下の子どもには食べさせないで!
小袋か豆に見立てた代替品をまく
今は、節分の時期になるとスーパーなどで小袋に入った福豆やお菓子が売られています。もし園で豆まきをするときは、豆そのものではなく、小袋のまま行うなどの工夫をするようにしましょう。また、豆や小袋に見立てたものを用意しておくのも方法の一つです。人がいない方に投げる
子どもたちと一緒に豆をまく時は、始める前に「お友だちや先生に向かって投げないようにしよう」と約束を決めてから行うようにしましょう。安全面にも気をつけながら、楽しく伝統行事に触れられると良いですね。節分の手作り遊びアイデア7選
節分の行事をさらに楽しむために、子どもたちとできる手作りゲームや製作アイデア、ペープサートキットなどを一気にご紹介します。①鬼のボーリングゲーム
②オニのかんむり
牛乳パック(飲料パック)を開くと、子どもたちの頭のサイズにぴったりのかんむり(お面)が作れます。今回は、節分の季節に向けてオニのお面にしてみました。廃材を使った工作のレパートリーとしてもいかがでしょうか?③オニの豆入れバッグ
豆まきに使えるかわいい豆入れバッグを製作しました。先生がオニ役になってレクリエーションをしても楽しいですね。オニの表情を変えたり、子どもたちが自由に描いてみたりするのもおすすめです。④牛乳パックでかわいいオニの豆入れ
節分におすすめの、楽しく遊べる豆入れの製作アイデアです。今回は牛乳パックを使って、枡(ます)のような四角い豆入れを作りました。かわいいオニに向かって「鬼は外!福は内!」とボールを投げながら、豆まきを楽しめます。リボンや紐をつければ、首から下げられる豆入れバッグにもなりますよ。⑤乳児クラスから楽しめる布おもちゃ
コラムでもお馴染みの人気布おもちゃ作家“ゆっこせんせい”が、節分に楽しめる布おもちゃゲームをご紹介します。⑥節分版シルエットクイズ・ペープサート


シルエットクイズ4種類
- 赤おに
- 青おに
- 豆まき
- ひいらぎいわし
⑦節分の折り紙と製作アイデアまとめ!
折り紙や、簡単に取り組める製作アイデアネタをまとめてみました。活動の参考にしてみてください。節分に楽しめる手遊び歌・ピアノ弾き歌い
せっかくなので、手遊び歌やピアノの弾き歌いで節分の導入をしてみましょう。こちらは定番の曲ですよね。おにのパンツ
なかなか破れない、丈夫なおにのパンツを歌にした手遊び歌です。原曲は、1880年に発表されたイタリアの大衆歌謡曲「フニクリ・フニクラ」。日本でも良く知られている曲なので、聞いたことがあるという方もいるかもしれませんね。定番の曲ですが、特に節分の時期にはぴったりなので、活動の導入などで取り入れてみてくださいね。 ピアノ弾き歌いの楽譜と遊びのアレンジについてはこちら!
節分に読みたいおすすめ絵本4選
「節分の説明をしたいけど、言葉で伝えていくのは少し難しい」。そんなときは、ぜひ絵本を活用してみてください。今回は、乳児・幼児それぞれに合わせたおすすめ絵本をご紹介します。①おにのパンツ

構成・絵:鈴木博子
出版社:ひさかたチャイルド
対象年齢:1、2歳~
遊び歌・手遊び歌としても大人気の「おにのパンツ」が絵本になっています。まだ行事そのものの意味を学ぶには難しい年齢のときには、行事にちなんだ「おに」に楽しく触れてみましょう。
描かれているイラストはとても可愛らしく、動物も登場するので、子どもたちも馴染みやすいのではないでしょうか。一緒に歌いながら節分を楽しんでみてくださいね。
②おなかのなかにおにがいる

作:小沢孝子
絵:西村達馬
出版社:ひさかたチャイルド
対象年齢:3歳・4歳・5歳~
「みんなのお腹の中には実は鬼がいて、その鬼は持ち主と同じ性格…!? 食いしん坊、泣き虫、めんどくさがり…いろんな鬼がいるけれど、自分のお腹の中にいるのはどんな鬼?」
ユニークな設定で子どもたちの想像力を掻き立てる1冊です。読み終わった後は、自分の中の鬼について盛り上がりそうですね。豆まきをしてお腹から追い出した鬼たちが、「おにはうち」の掛け声でお腹の中に飛び込んでいくシーンが面白い、ぜひ一度は読んでほしいおすすめ絵本です。
③まめのかぞえうた

作:西内ミナミ
絵:和歌山静子
出版社:鈴木出版
「ひとーつ まめ ひとつ あったとさ」数を数えながら豆が成長していく、楽しい数え歌です。
数を学びながら、豆が成長していく可愛い過程を見られるほっこりする絵本です。乳児クラスから楽しめるので、節分そのものを楽しむよりもまずは関連するものに触れてほしい! というときにおすすめです。表紙に描かれたたくさんの豆も可愛いですね。お気に入りを子どもたちと探してみてください♪
④おばあちゃんのえほうまき

作・絵:野村たかあき
出版社:佼成出版社
きりちゃんは、おばあちゃんと一緒に「恵方巻き」を作ります。恵方巻きって? どんな意味があるの? 行事食を手作りする楽しさを伝えてくれます。
節分には欠かせない恵方巻きについて、絵本で楽しむ学ぶことができます。巻末には恵方巻きのレシピもついているので、実際に食育で作ってみるのも良いですね。
伝統行事を楽しもう
日本に昔から伝わる行事として、子どもたちにも節分の由来や楽しみ方を知ってほしいですよね。園での活動をきっかけに、伝統行事が受け継がれていくことを願います。【関連記事】