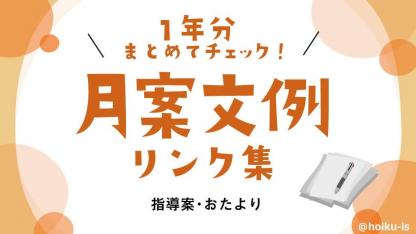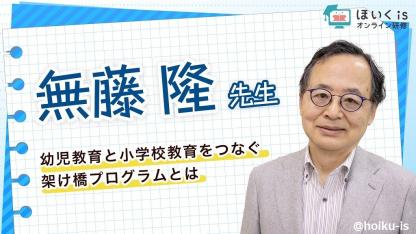保育のポイント【2歳児・7月】
水遊びやプール遊び、七夕祭りなど、楽しい行事が盛りだくさんの7月。暑くなるので体調管理をしっかり行いながら、夏ならではの活動を楽しみましょう。この頃になると、自分でできることもどんどん増えていき、自分ひとりでやりたがる姿も多く見られます。子ども同士の交流も活発になり、自分たちの発想で遊びを楽しむようになるでしょう。子どもの「やりたい」気持ちを尊重しながら、保育者は見守る保育を実践できるといいですね。

ねらい【2歳児・7月】
- 身の回りのことを自立して行う。
- 水分補給や休憩をしながら、健康に過ごす。
- 他児と共通のイメージを持ちながら遊ぶ。
- 集団生活をする中でのルールやマナーを学ぶ。
- 水遊びを通してモノの性質に興味を持つ。
- 七夕祭りを通して、伝統文化に親しむ。
- 語彙が増え、自分の気持ちを伝えたり体験を話したりする。
- 自分の好きな色を使って七夕製作を楽しむ。
内容/五領域対応【2歳児・7月】
- 手洗いや片付けをする場面が分かり、自ら積極的に行おうとする。(健康)
- 外遊びのときはこまめに休憩をして水分を摂り、夏の暑さに負けないように健康に過ごす。(健康)
- 他児との関わりの中で、「お店屋さんごっこ」「保育園ごっこ」など共通のテーマを決めてごっこ遊びを楽しむ。(人間関係)
- 玩具や水道、トイレなどの順番待ちや譲り合い、公園での遊具の使い方など集団で生活する中で必要なルールやマナーを知り、守ろうとする。(人間関係)
- 色水遊びや泥遊び、じょうろや水鉄砲などの容器を使った遊びで水に触れ、感触や見た目の変化に疑問を持ち知ろうとする。(環境)
- 七夕祭りで織姫と彦星のお話を聞いたり、行事食を食べたりしながら行事を楽しむ。(環境)
- 昨日あった出来事を話したり、自分が感じたことを伝えたりしながら会話を楽しむ。(言葉)
- 好きな色の画用紙を選び、シールを貼ったり絵を描いたりして短冊を作る。(表現)
| ※「内容」については、例文の最後に保育所保育指針にある五領域のどれに対応しているか表示をしています。 ・健康(心身の健康に関する領域) ・人間関係(人とのかかわりに関する領域) ・環境(身近な環境とのかかわりに関する領域) ・言葉(言葉の獲得に関する領域) ・表現(感性と表現に関する領域) |
内容/養護【2歳児・7月】
- 戸外活動の後は、汗を拭いたり、こまめな着替えや水分補給を欠かさないようにする。
- 友だちや保育者と一緒に、安心して遊びが楽しめるような環境を整える。
- 熱中症の兆候や体調の変化に気付けるよう、視診や必要に応じた検温を実施する。
- 自分で石鹸を使って手洗いをしようとする気持ちを大切にしながら見守り、必要に応じて手伝う。
環境構成・保育者の配慮【2歳児・7月】
- 子どもたちが自分で考えてできるように、手洗いのやり方をイラストにしたものを水道の壁に掲示する。
- 気温に合わせて外遊びの時間を調節したり、日陰で休憩したりしながら遊ぶ。
- ごっこ遊びを展開しやすいよう、お金やレジなど遊びに合わせた手作り玩具を用意する。
- 公共物や公共の場所の使い方に関する絵本を読んだり、順番待ちの場所に足形シールを貼ったりする。
- さまざまな形で水に触れられるよう、色水遊び、砂場での泥遊び、容器や器具を使った遊びなどを計画する。
- 七夕を題材にした絵本の読み聞かせを行う。
- 言葉でのやり取りを楽しめるよう、子どもの話を遮らないように受け止めながら聞く。
- 製作物の色の指定は行わず、画用紙やクレヨンの色を自由に選べるようにする。
予測される子どもの姿【2歳児・7月】
- イラストを見たり、絵本や歌で覚えた洗い方を再現したりして手洗いをする。
- 遊びたい気持ちから休憩や水分補給を嫌がることがある。
- 自分が体験したことをごっこ遊びに取り入れたり、保育者や保護者の言動を模倣したりして遊ぶ。
- 初めは順番待ちができなかったり玩具を取り合う姿が見られるが、少しずつ保育者の声かけがなくても待ったり「どうぞ」と譲ったり待つ姿が増える。
- 流れていく水の性質に興味を持ち、さまざまな道具を使って水をつかまえようとする。
- 七夕のおおまかな意味を知り、製作やゲームで行事を楽しむ。
- 言葉が増えて会話が上手になり、保育者や他児とのやり取りを楽しむ姿が増える。
- 好きな色を使って短冊製作を楽しみ、保育者に手伝ってもらいながらお願い事を書こうとする。
前月の子どもの姿【2歳児・7月】
- できることが大幅に増え、ひとりで何でもやってみようとする姿が多く見られた。中には保育者の手助けを嫌がる子もいて、自立心が強くなっていることを感じた。
- 友だちと同じ遊びを一緒に楽しむことを好む様子が多く、ごっこ遊びがとくに流行っていた。お店屋さんごっこが好きで、体験したことを表現しながら楽しんでいた。
家庭や地域との連携【2歳児・7月】
- おたよりや連絡帳を使って水遊びについての注意事項や持ち物を知らせる。
- 汗をかきやすくなるので、着替えやタオルのストックをロッカーに置いてもらう。
健康や安全【2歳児・7月】
- 気温や湿度に注意して、換気や除菌をしながら快適に過ごせる環境を整える。
- 感染症予防のため水遊びをするときは子どもたちの密集を避け、感覚的に余裕をもって遊ぶ。
食育【2歳児・7月】
- 収穫した食材を給食に取り入れ、食べ物に愛着を持つことでより食を楽しむ。
- スプーンやフォークを使い、下手持ちで食べる。
今月の行事【2歳児・7月】
- 身体測定
- 七夕会
- 水遊び
- 避難訓練
- お誕生日会
今月の遊び【2歳児・7月】
水や泥などの感触を楽しみ、五感を刺激する遊びがおすすめです。- 色水のセンサリートイ
- 寒天遊び
- 水鉄砲で!的当てゲーム
- 風船タッチ
- 砂遊び・泥んこ遊び
今月の歌・手遊び歌・体操【2歳児・7月】
7月の歌
- うみ
- きらきらぼし
- あいあい
- いるかはザンブラコ
- たなばたさま
7月の手遊び歌
- なっとう
- さかながはねて
- にゅうめんそうめん
- ぼうがいっぽん
7月の体操
- パイナポー体操
- エビカニクス音頭
今月のおすすめ絵本【2歳児・7月】
- みずちゃぽん
- おまつり
- はなびドーン
- こぐまちゃんのみずあそび
自己評価【2歳児・7月】
6月は梅雨に入り、室内遊びの機会も増えたのではないでしょうか。子どもたちも雨で外に出られない日が続くと、ストレスが溜まります。そのときの体調の変化をしっかりと察知したり、室内でも身体を動かせる遊びを取り入れたりできたかどうかを振り返ってみましょう。日々子どもたちの体調の変化を見落とさないことも、保育者の大切な役割のひとつですね。
2023年度版フォーマットのダウンロード【2歳児・7月】
ほいくisメンバー登録(無料)をすると、Excel形式で“そのまま使える”月案/週案フォーマット(月週案)を無料でダウンロードすることができます。また、文例だけプリントして使いたい方のためにPDF版もご用意しました。ぜひご利用ください。
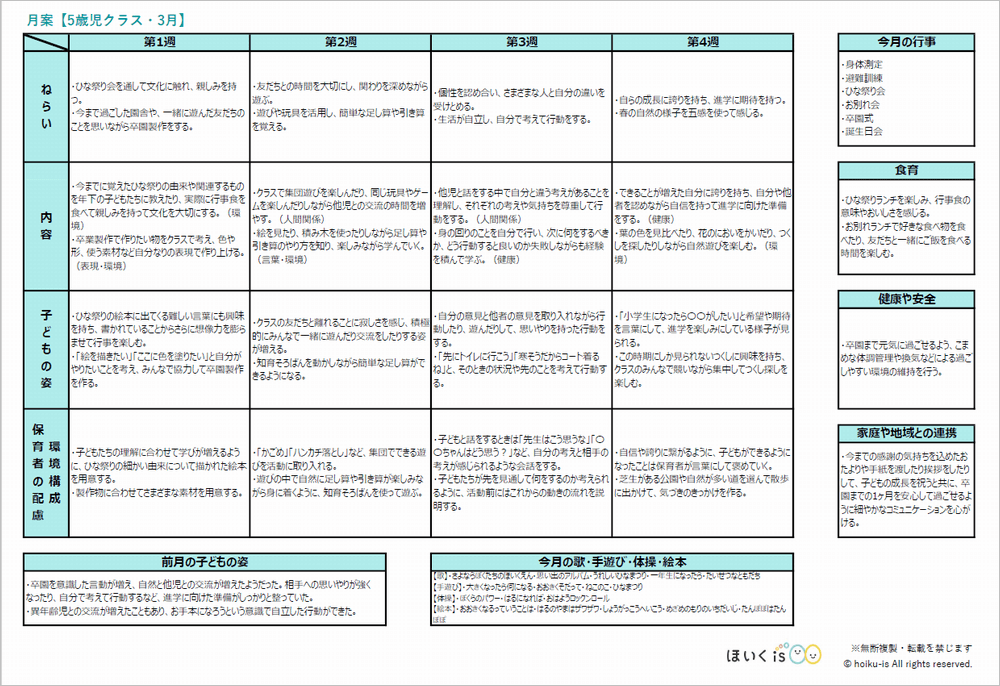
PDF版の月案文例【2歳児・7月】

自分の言葉で作る意識を
参考文例をお届けしましたが、あくまで指導計画は自分の言葉で作ることが大切です。一つひとつの事例を参考にしながら、少しずつ自分の考えを入れていくよう工夫しましょう。【関連記事】
>>指導案・おたより一覧